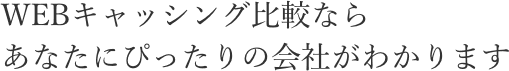例外的に年収の3分の1以上の融資を受けられる!
総量規制の「除外」と「例外」とは

「総量規制」とは借り手を守る為の法律で、貸金業者は借り手の年収の3分の1を上回る融資が禁止されています。しかし急病・ケガや自宅購入時など、多額の融資が必要な場合は例外的に規制額以上の貸付けが可能です。この記事では、総量規制における除外項目と例外項目についてまとめました。
年収の3分の1以上の融資が必要なときはどうすればいいの?
現在の貸金業法は2006年から段階的に施行され、2010年6月以降は「総量規制」も含めたすべての項目が最新版に切り替わりました。総量規制とは、法改正前に頻発し社会問題になっていた、自己破産にいたる多重債務者を減らすために設けられた規制です。
複数の貸金業者から融資を受けている場合でも、借入総額の上限は年収の3分の1までと定められました。貸金業法の対象外である銀行ローンが抜け道として利用されていましたが、2017年11月以降は銀行も貸金業法にならって自主規制を始めています。
総量規制は借り手を守るためにありますが、自身の年収の3分の1を上回る融資が必要な場面があるのも事実です。そのため総量規制には「除外」と「例外」が設けられています。
除外
- 不動産購入または不動産に改良のための貸付け(そのためのつなぎ融資を含む)
- 自動車購入時の自動車担保貸付け
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券担保貸付け
- 不動産担保貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
- 手形(融通手形を除く)の割引
- 金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
- 貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(施行規則第10条の21第1項各号)
例外
- 顧客に一方的有利となる借換え
- 緊急の医療費の貸付け
- 社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
- 配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
- 個人事業者に対する貸付け
- 預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
(施行規則第10条の23第1項各号)
総量規制の除外項目
「除外」とはそもそも総量規制の対象にならない融資のことです。
例えば、たいていの人はマイホームを買うときに30年や35年などの長期ローンを組みますよね。マイホーム購入に必要な金額は、ほとんどの場合借り手の年収の3分の1を上回っています(上回っていない人は一括で払えます)。自動車も同じです。
また急に長期の入院や大きな手術が必要な病気に罹ったり怪我をしたりすることもあるでしょう。こういった場面でも総量規制が適用されてしまうと、マイホームが買えない、治療費が払えないといった事態が頻発します。
それを防ぐために、貸金業法施行規則第10条の21 第1項各号に、総量規制から除外される項目が定められています。主な除外項目について解説します。
不動産購入または改良のための貸付けとつなぎ融資
土地・戸建て住宅・分譲住宅の購入や、マイホームの建設・リフォームに必要な融資に適用されます。
銀行の住宅ローンやリフォームローンを利用するのが一般的ですが、条件が合わなかったり、審査が遅かったりする場合があります。そういうときは貸金業者から融資を受けられます。
また、銀行から融資が下りる前に支払いが発生した場合、つなぎとして一時的に資金が必要になります。こういう場合の「つなぎ融資」も除外項目に含まれます。
自動車購入時の自動車担保貸付け
「自動車クレジット」「ディーラーローン」と呼ばれるローンのことです。一般的に自動車を購入するときに組めるローンは、銀行が行っている「自動車ローン」か、ディーラーが行っている「ディーラーローン(自動車クレジット)」の2種類です。
「ディーラーローン(自動車クレジット)」とは、いったん信販会社がディーラーに購入費用を支払い、購入者は信販会社に対してローンを支払っていく方式のことです。購入した自動車が担保になっているので、支払いが終わるまで自動車の所有権は信販会社にあります。
よく勘違いされるのが、貸金業者による自動車ローンです。自動車を担保に入れ、貸金業者から自動車の売却額相当の融資を受けるのは、ディーラーローンとは別物です。総量規制の除外対象にはなりませんので注意してください。
高額療養費の貸付け
手術や入院が必要な傷病の療養費は高額になります。高額療養費には補助があって、申請すれば支払いの大部分が返還されます。しかし補助が下りるまでには時間がかかるので、療養費の支払いには間に合わないことがあります。
療養費が高額すぎて年収の3分の1を超えてしまう場合も、すでに融資限度額いっぱいまで借りている場合も、高額療養費の支払いに必要な額は融資してもらえることになっています。
有価証券担保貸付け
有権証券とは「国債」「小切手」「手形」「株券(株式)」など、お金(金券)以外の、私的な財産を示す証券のことです。証券の種類や発行元の信用力によって、担保評価(担保となった有価証券に対して、何割程度の融資が下りるか)が違います。
「国債」は日本という国が発行しているもので、日本が破綻しない限り換金できる有価証券なので、担保評価は90%近くにもなります。
不動産担保貸付け
不動産、つまり土地や建物は資産にカウントされます。売却すれば返済資金になるので、総量規制の対象からは除外されるという考え方です。
新しい不動産を購入する場合以外にも、すでに受けている融資を不動産担保ローンに借り換えることで、総量規制の対象となる枠をあけることも可能です。
返済できなくなった場合、担保にした不動産は当然没収されてしまうので注意してくださいね。
売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
不動産担保貸付けと似ていますが、この場合、不動産は手放します。不動産売却による収入が発生する前に支払いが必要な場合のつなぎ融資扱いです。
その他の除外項目
・手形(融通手形を除く)の割引・金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
・貸金業者を債権者とする金銭賃借契約の媒介
以上の3つも総量規制からは除外されますが、個人が受ける融資にはあまり関係ないでしょう。
総量規制の例外項目
人生には何があるかわかりません。除外項目以外でも、年収の3分の1以上のまとまった額の現金が必要になることはあります。例えばすでに年収の3分の1近く借り入れている人が急病で倒れることなどは容易に想像がつきますよね。
借入総額が年収の3分の1を上回ってしまうけれど、どうしても必要な場面に対応するために、「除外」のほかに「例外」も設定されています。貸金業法施行規則第10条の23 第1項各号に定められています。以下に例外項目をまとめました
・顧客に一方的有利となる借換え・緊急の医療費の貸付け
・社会通念上緊急に必要と認められる費用を支払うための資金の貸付け
・配偶者と併せた年収の3分の1以下の貸付け
・個人事業者に対する貸付け
・預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け
例外とされているのは、返済をスムーズに済ませるための融資や、緊急事態を乗り切るための融資です。急病や冠婚葬祭のような避けようのない出費で破産することがないように配慮されています。
個人事業主の方はビジネスローンも併せて検討してください。
まとめ:正当な理由があれば規制額以上の借入が可能です
一律で年収の3分の1までしか借入れられないという規制があると、困ってしまう場面は結構たくさんあります。もちろん除外や例外と認められるためには厳しい与信審査に通らなくてはいけません。
しかし逆に考えると、正当な理由があれば融資を受けることは可能なので、急な出費に絶望する必要はありません。事情がある場合は公的機関・各金融機関に相談してみましょう。